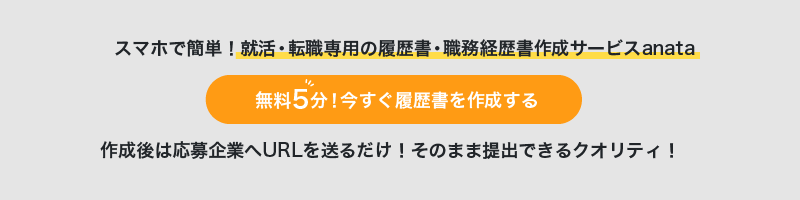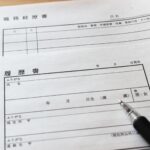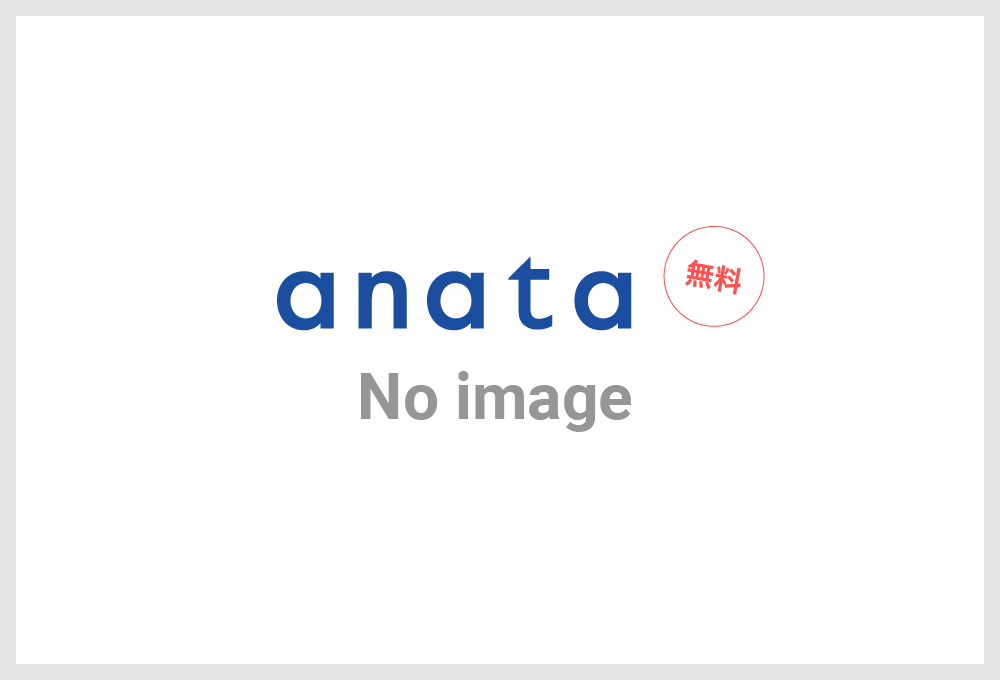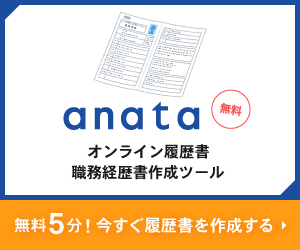履歴書の扶養家族数の書き方。5ケース別の扶養家族数の数え方も解説
- 履歴書
- 転職ノウハウ


オンライン履歴書・職務経歴書作成ツール

スマホで簡単!就活・転職専用の履歴書・職務経歴書作成サービス!
作成後は応募企業へURLを送るだけ!そのまま企業へ提出できるクオリティ!
目次
扶養家族の存在は多くの人にとって重要なポイントであり、それを履歴書にどのように記載するかは、しばしば頭を悩ませる問題となります。特に、「扶養家族とは何?」という基本的な定義から、「履歴書の扶養家族欄の書き方を知りたい」という具体的な疑問まで、さまざまな情報が求められています。この記事では、扶養家族の基本的な定義から履歴書での記載方法、そして5つの異なるケースにおける扶養家族数の数え方について明確に解説します。
扶養家族とは

扶養家族は、個人の収入に依存する家族を指し、履歴書においては主に社会保険上の扶養家族が記入対象となります。この記入は、税金計算や保険手続きの事前理解を助ける目的があります。また、扶養家族の定義は税法と社会保険法で異なり、一例として、被保険者とは別の社会保険に加入している家族は扶養家族に含まれません。これらの法律に基づく定義の違いを理解することが重要で、正確な扶養家族数の記入につながります。
扶養家族の範囲とは
扶養家族の範囲は特定の規定により定められています。具体的には、配偶者や18歳未満の子ども、または60歳以上の直系尊属といった親族が扶養家族として認められます。これらの家族は、あなたの収入に依存して生活していることが前提となります。一方で、75歳以上の人々は通常、後期高齢者医療制度の加入者となるため、これらの人々は扶養家族に含まれません。扶養家族の範囲を正確に理解し、履歴書に正しい家族数を記入することが重要です。また、各家族の年齢や健康状態、そして他の条件によっても扶養家族としての認定が変わる可能性があるため、常に最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することも重要であることを覚えておきましょう。
扶養家族として認められる収入条件
扶養家族として認められる収入条件は非常に重要で、これによって履歴書に記入する家族の数が決まります。条件は主に被扶養者の年齢と収入、そして扶養者と被扶養者の住居状況に分かれます。
まず、同居している場合の条件を見てみましょう。被扶養者が60歳未満の場合、年間収入が130万円未満で、かつ被扶養者の収入が扶養者の収入の半分以下である必要があります。さらに、被扶養者が60歳以上か、もしくは59歳以下の障害者である場合は、年間収入が180万円未満で、被扶養者の収入が扶養者の収入の半分以下であることが求められます。
次に、別居している場合の条件を確認します。このケースでは、被扶養者の年間収入が130万円未満で、扶養者が被扶養者に対して継続的に仕送りを行っていて、その仕送りが被扶養者の収入よりも多い必要があります。但し、106万円以上の年収で勤務先の社会保険の加入対象になっている人は対象外となります。
これらの経済的条件を満たしているにも関わらず、被保険者以外に主な支援者がいる場合、扶養家族としては認められません。これらの点を踏まえ、正確な扶養家族数を把握し、履歴書に適切に記載することが重要です。
履歴書の扶養家族数の書き方

本章では、履歴書における扶養家族数の書き方をいくつかのケースに分けて解説しています。
- 扶養家族数の書き方
- 配偶者の書き方
- 配偶者の扶養義務の書き方
- 学生の場合
履歴書の扶養家族数欄を適切に記入し、正確な家庭状況を採用担当者に伝えましょう。
扶養家族数の書き方
履歴書作成における「扶養家族数」の記載は、自分がどれだけの家族を経済的に支えているのかを示す重要な項目です。
まず、「扶養家族数」欄には、自分を除く扶養家族の人数を記入します。例えば、配偶者と子供2人を扶養している場合、「3」と記入します。また、子供が配偶者の扶養に入っている場合は、その子供の数はカウントしません。この情報は、採用担当者が家庭状況を理解するのに役立ちます。加えて、多くの履歴書テンプレートでは「扶養家族数(配偶者を除く)」と指定されている場合があります。この場合は、配偶者を除いた家族の人数を記入しましょう。
配偶者の書き方
個人の家庭状況を明示することで、企業は候補者の背景をよりよく理解することができます。以下に配偶者の書き方について簡潔に説明します。
まず、履歴書の配偶者欄には、「有」または「無」のいずれかを明示します。該当する項目に◯を記入し、不要な項目は空白にします。また、履歴書の指示に従って、配偶者の有無を正確に記入しましょう。これは、企業が候補者の家庭状況を適切に評価するのに役立ちます。
このように、配偶者の記述は直接的かつ明確であるべきであり、事実婚の状況を正確に反映することが重要です。
配偶者の扶養義務の書き方
配偶者が被扶養者として認定されているか、または健康保険に加入していないかを確認することが必要です。認定されている場合や健康保険に未加入である場合は、「有」と記述します。一方、配偶者が被扶養者条件を満たさない、または自ら健康保険に加入している場合は、「無」と記述します。この項目は、配偶者が自身の収入を持っているか、または別の健康保険制度に加入しているかを採用担当者に明示するために重要であり、適切な表記を心がけることで、採用プロセスをスムーズに進めることができます。
学生の場合
学生の場合でも、履歴書に扶養家族数の欄があるため、正確な情報を記入することが求められます。扶養家族とは、基本的に3親等以内の家族で、同居しているか、あるいは経済的に支援している別居親族を指します。しかし、学生がまだ収入を得ていない場合、扶養家族数は「0」と記載することが一般的です。一方で、アルバイトなどで収入を得ていて家族を扶養している場合は、その家族数を正確に記入します。この欄は、採用担当者が求職者の家庭状況を理解するために重要であり、正確な情報提供は信頼性を示すものとなります。学生であっても、履歴書作成時には家庭状況を正確に把握し、適切な情報を提供することが求められます。
5ケース別の扶養家族数の数え方

扶養家族数の数え方は個人の家庭状況によって異なります。以下に示す5つのケースでは、それぞれの家庭状況における扶養家族数の計算方法を明示し、読者に対して明確な指針を提供します。これにより、履歴書作成時に求職者自身の家庭状況を適切に反映させることができます。
- 独身の場合
- 独身で同居もしくは別居している父母(2人)を養っている場合
- 結婚をしていて配偶者が専業主婦(夫)の場合
- 結婚をしていて夫婦共働きの場合
- 別居している親族がいる場合
このセクションでは、各ケースに応じて扶養家族数をどのように記載すればよいのか、明確な指南を提供します。
独身の場合
独身の場合の扶養家族数の記入は、家庭状況によって異なります。配偶者や配偶者の扶養義務はないため、主に親や兄弟との関係が影響します。同居または仕送りをしている親族がいて、その生計を支えている場合には、扶養家族としてカウントすることができます。具体的には、父母が同居していて、かつ自分の収入で生計を支えている場合、扶養家族数は「2」人と記入します。しかし、親族とは別居で、仕送り等の支援を行っていない場合、扶養家族数は「0」人と記入します。このように独身者でも、家庭状況によって扶養家族数は変動するため、正確な家庭状況を理解し、履歴書に適切に反映させることが重要です。
独身で同居もしくは別居している父母(2人)を養っている場合
独身者であっても、親族の生計を支えている場合には履歴書の扶養家族数欄にその人数を記入する必要があります。特に父母のケースでは、同居であるか別居であるかに関わらず、主な生活費を送金または負担している場合に扶養家族としてカウントできます。具体的には、同居または別居している父母を養っている場合、扶養家族数は「2」人と記入します。一方、親族に対して経済的な支援を行っていない場合は、扶養家族数は「0」人と記入します。この記入方法は、求人側が応募者の家庭状況や責任を理解する手助けになります。また、扶養家族数の正確な記入は、税務や社会保険の手続きにも影響するため、重要なポイントとなります。
結婚をしていて配偶者が専業主婦(夫)の場合
結婚していて配偶者が専業主婦(夫)である場合、履歴書の扶養家族数の記入は特に重要になります。このケースでは、夫(扶養者)の収入で生計を立てている家族の人数を扶養家族数として記入します。具体的には、夫、妻、そして収入のない子供や親族を扶養家族数としてカウントします。
例えば、夫の母親が同居していて収入がない場合、扶養家族数に含めることができます。この場合、扶養家族数は「2」人(妻と母親)となります。さらに、子供がいる場合は子供の数だけ扶養家族数が増えます。
扶養家族数の記入は、税金や社会保険の手続きに影響を与えるため、正確に記入することが求められます。また、扶養家族の状況は求職活動においても重要な情報となるため、適切に記入し、家庭状況を正確に伝えることが大切です。これにより、求人側は応募者の家庭状況や責任を理解し、適切なサポートや配慮を提供することが可能となります。
結婚をしていて夫婦共働きの場合
結婚していて夫婦共働きの場合、履歴書の扶養家族数の記入は家族の収入状況によって変わります。ここでは、家族それぞれの収入が扶養家族数にどのように影響するかを理解することが重要です。
具体的な例を挙げると、夫と妻、そして子供の収入状況によって、配偶者の扶養義務と扶養家族数が異なります。収入が130万円未満の家族は扶養対象となり、それに基づいて扶養家族数が決まります。
例えば、夫と妻が共に収入を得ているが、年間収入が130万円未満である場合、配偶者および子供は扶養家族となります。この状況下で、夫または妻が扶養家族の主となり、扶養家族数を計算し、履歴書に記入します。一方、夫と妻の収入が130万円以上である場合、扶養家族数は子供の数に依存します。
扶養家族数の正確な記入は、税金や社会保険の手続き、そして求職活動においても重要な情報となります。このため、夫妻共働きの家庭でも、家庭の収入状況を正確に把握し、扶養家族数を適切に記入することが求められます。
別居している親族がいる場合
別居している親族がいる場合でも、特定の条件下で扶養家族としてカウントすることが可能です。主な条件は扶養者が親族に対して主な生活費を仕送りしていることです。具体例として、夫、妻、子供がいて、夫の母が別居している場合、夫の母の生活費を夫が支えている場合には、扶養家族数に夫の母を含めることができます。このように、別居している親族の扶養家族としての扱いは、扶養者の経済的支援の有無に依存します。それゆえ、履歴書を記入する際には、別居している親族の状況を正確に把握し、適切に扶養家族数を記入することが重要となります。
履歴書の扶養家族数に関するよくある質問

本章では、履歴書の扶養家族数に関連する一般的な疑問を解説します。下記疑問を明確にし、履歴書を記入する際の不安を軽減しましょう。
- 履歴書の扶養家族・配偶者欄を見て採用担当者は何を確認していますか?
- 扶養家族数や配偶者の有無は選考に影響する?
- 事実婚をしている場合は配偶者に当てはまりますか?
履歴書の扶養家族・配偶者欄を見て採用担当者は何を確認していますか?
履歴書の扶養家族・配偶者欄は、採用担当者にとって個人の家庭状況を把握するための情報源となります。しかし、この情報は通常、書類選考の合否を決定する主要な要因ではありません。企業は、福利厚生プログラムや保険手続きに必要な情報を事前にチェックするためにこの欄を確認します。正確な記載は求められており、これによって企業は求職者が指示を適切に理解し、正確に履歴書を記入する能力を持っていることを確認できます。記入ミスは、求職者の注意深さや指示に従う能力に疑問を投げかける可能性があり、採用プロセスにおいてマイナス要因となる可能性があります。このため、ルールに従って欄を漏れなく正しく記入することが重要となります。
扶養家族数や配偶者の有無は選考に影響する?
扶養家族数や配偶者の有無は、採用プロセスにおいて一定の影響をもたらすことがあります。これらの情報は、求職者の働き方やキャリアプランに影響を与える可能性があり、採用担当者はこれらの情報を利用して求職者の制約や懸念点を理解しようとします。扶養家族欄は、入社後に求職者と企業の間でミスマッチが発生しないように、また、求職者の責任や優先事項を把握するために重要なツールとなります。
ただし、これらの情報だけが求職者の採用選考に影響を与えるわけではなく、スキル、経験、適性などの他の重要な要因も総合的に評価されます。求職者が自身の働き方やキャリアプランについて明確に説明し、それが企業のニーズや期待と合致している場合、扶養家族数や配偶者の有無は選考に大きな影響を与えない可能性が高まります。
事実婚をしている場合は配偶者に当てはまりますか?
事実婚においても、法律上の配偶者と同様にパートナーを履歴書の配偶者欄に記載することが一般的です。しかし、この記載は企業や業界、そして国や地域の法律や規定によって異なる場合があります。事実婚のパートナーを配偶者として履歴書に記載する際には、事実婚の証明が求められることもあります。これには、共同生活を証明する書類や、共有の資産や財務情報などが必要とされる場合があります。
また、社会保険の加入においても事実婚のパートナーが配偶者として認められるかどうかは、社会保険の制度や法律に基づいて判断されます。これらの制度は地域や国によって異なり、事実婚のパートナーが法律上の配偶者と同等に扱われるかどうかを決定します。
このため、事実婚の状況を明確にし、必要に応じて適切な証明書類を準備し、そして求人企業の指示や要求に従って履歴書を記入することが重要です。これにより、事実婚のパートナーを正確かつ適切に履歴書に記載し、選考プロセスを円滑に進めることができます。
まとめ

履歴書の扶養家族数の記入は、個人の家庭状況を正確に反映させる重要な部分です。扶養家族の数や配偶者の有無を適切に記入することで、企業は候補者の生活状況を理解し、必要に応じて支援を提供することが可能となります。本記事では、独身、既婚、子供の有無、学生、別居家族など、さまざまなケースにおける扶養家族数の数え方を解説しました。また、履歴書の扶養家族数に関するよくある質問にも答え、採用担当者がこの欄から何を見ているのか、選考にどのように影響するのか、事実婚の扱いについても明示しました。
また、WEB履歴書・職務経歴書作成サービス「anata」を利用すれば、Excel不要で簡単に履歴書を作成できます。ブラウザで無料作成、URL送信可能、PDF保存も容易です。スマホさえあればすぐ作成でき、アカウント登録で後から編集も可能。履歴書作成の効率化をanataで実現しましょう。